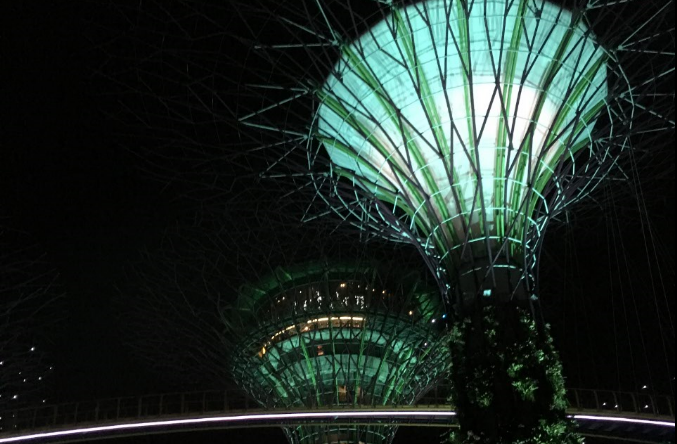最終更新日: 2025年06月09日
グローバル文化専攻・現代文化システム系 先端社会論コース
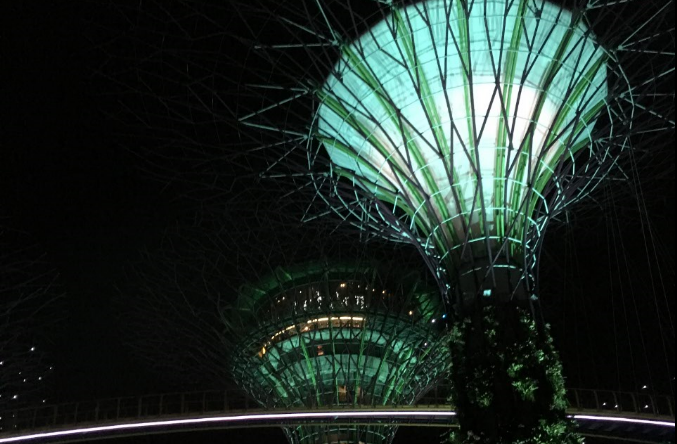
現代社会では、人間・自然・社会の相互関係が大きく揺らぎ、ますます複雑化してきています。「先端社会論」コースは、この現代杜会の先端的な問題群を、人文・社会科学を交差する学際的アプローチによって、領域横断的に検討することを課題としています。例えば、性差を社会的に構成されたものととらえるジェンダー論の視点から、家族や個人や国家をめぐる考え方の変化を分析すること。貧困、移民・難民、人権侵害、体制転換などのグローバルかつトランスナショナルな課題の公正な解決法を構想すること。メディア・テクノロジーの革新が促進する消費社会の情報化と多文化社会が要請する新たな社会観や人間観を模索すること。「先端社会論」コースは、こうした錯綜する諸問題を理論的に解きほぐし、それらに現実的に対処していくためのトレーニングの場です。
| 進路実績 | (前期課程) 兵庫県庁、富士通BSC、(株)三菱倉庫、(株)コベルコシステム、ほか (後期課程) 花園大学文学部創造表現学科准教授、京大グローバルCOE研究員、ほか |
|---|
| 在籍学生数 | (前期課程) 6名
(後期課程) 7名 |
|---|
| 論文テーマ例 | (前期課程)
Representation of Romanies in Tony Gatlif’s Films
<私>のこの眼差しは、誰のものか―パク・チャヌク『お嬢さん』における「男性の視線」の流用をめぐるオートエスノグラフィー
「脆弱な女性たち」が問い直すネパールにおける女性運動―バディ女性の運動から
日本型雇用システムにおける差別と抵抗―トランスジェンダーの新卒就職活動に注目して
在日中国籍技能実習生の階層帰属意識
「二人っ子政策」における女性の「産む・産まない」自己決定の葛藤―潮州女性の人生の歩みを通して
近親者へのカミングアウトの有無がセックスワーカーの生活に与える影響
Intersectionality and Employment: Discrimination Against MuslimWomen in the Process of Job-Seeking in Japan
ディアスポラ・イン・ゼア・オウン・ランド――映画『告別』における中国籍モンゴル人のアイデンティフィケーションについて (後期課程)
日中における『シャーロックホームズ』の受容
Diffusion of Hip Hop: A Critical Reappraisal of‘Call and Response’in the East Asian Street Dance Culture
Rethinking Queer Migrant Experience through the Lens of Drag Performance
宝塚歌劇における「女同士の絆」
Tōjisha Eiga : An Analysis of Representations of Sexuality in
Hashiguchi Ryōsuke’s and Imaizumi Kōichi’s Filmmaking
‘Capitalistic Rituals’ in Football: The Case of Vissel Kobe Fandom
in Japan |
|---|
| 所属教員の紹介 | 青山 薫 教授 ジェンダー社会文化論特殊講義ほか
専門は社会学、ジェンダーとセクシュアリティ。 グローバル化、多文化主義、社会的排除と包摂、親密権、表象の問題などに関心を持ち、移住、ケア/性労働、同性婚、性同一性「障害」など、公私にわたる変化を引き起こす事象について、理論・方法論・実証研究を結びつけて追求しています。 小笠原 博毅 教授 メディア社会文化論特殊講義ほか
専門は社会学、カルチュラル・スタディーズ、現代イギリス研究。とくにメディアとスポーツをフィールドとして多文化資本主義と人種差別の文化との関係を、実証的、理論的、かつ思想史的に検証し考察しています。 西澤 晃彦 教授 現代社会理論特殊講義ほか
専門は社会学、都市社会学、社会問題論。社会的排除と貧困を主たるテーマとして、自己アイデンティティの構築・社会的世界の形成・都市空間の構成と社会的排除の関連について研究を行なってきました。 工藤 晴子 准教授 文化規範形成論特殊講義ほか
専門は国際社会学、難民・強制移動、クィア移住。人の国際移動とジェンダーやセクシュアリティの関わりについて特に難民・強制移住におけるセクシュアリティの規範という視点から研究しています。また難民支援の実務経験から、支援の暴力性や支援者/被支援者の権力関係という問題にも取り組んでいます。 |
|---|

白井 望人さん(博士前期課程 1 年)
神戸大学国際人間科学部卒業
研究テーマ:「ゲイ・バイセクシュアル男性のライフコースとそれに関する考え方についての研究」
先端社会論コースは、現代社会の様々な問題について、様々なアプローチで研究をしている先生方や学生がたくさんいます。こう書くと、「何をすればいいのかわからない!関心がバラバラで効率的に学べないのではないか?」と思う人もいるかもしれません。しかし、このコースで色々なことを学び、先生方や学生と議論していくなかで、バラバラだと思っていた様々な問題が、意外なところで結びついているんだと発見するときが必ず来ます。
私は、ゲイやバイセクシュアル等の「男性に惹かれる男性」が、女性と結婚するのか、男性と連れ添っていくのか、そして男性たち自身が様々な生き方の選択肢をどのように捉えているのかに興味があり、研究しています。このテーマにぴったり合う研究をしている先生や学生は周りにいないのですが、むしろそのことが自分ひとりでは考え付かなかった視点を提供してくれたり、考えもしなかった現象と自分の関心が結びついていることの発見につながりました。
そして、そのような議論が活発にできる雰囲気が先端社会論コースにはあります。先生方は気軽に議論をしてくれるので、お忙しい中でもしょっちゅう時間を作っていただき、たくさんアドバイスをもらえます。おかげさまで、修士課程のうちに雑誌に論文をひとつ掲載することができました。また、学生同士も仲良く、学部時代よりも友達が出来ましたし、色んな議論が出来て「学生」をしているな!と強く感じます。自分の研究に限らず、決して他人事ではない様々な現代社会の課題について、色々な視点で考えることができる能力を養える点で、とてもおすすめのコースです。
神谷 穂香さん(博士後期課程 2 年)
学習院大学人文科学研究科修了
研究テーマ:「現代日本のセックスワーカーによる発信について」
私は現代日本のセックスワーカーによる発信、具体的にはエッセイ、SNS での投稿、YouTube 動画などを対象に勉強しています。博士前期課程までは他大学に在籍していましたが、当時の指導教員の退任を機に、このテーマにおいて代表的な研究者でいらっしゃる青山薫先生のもとへ進学することを決めました。
先端社会論コースでは、自分の専門性を磨きつつ同時に分野を越えた勉強をすることが可能です。これは、本コースの先生方の専門がさまざまであること、他のコースと合同で利用する院生研究室において多様な関心を持つ学生と交流できることなどから感じます。また、研究科の特徴として留学生が多いため、日常的に英語を使い、異なるルーツを持つ者同士で刺激を受け合っています。
授業以外では、国際文化学研究推進インスティテュートの主催で定期的にセミナーが行われるため、他大学の先生や学生とも交流の機会を持つことができます。さらに本学は、博士後期課程の学生へのキャリアアップ支援が手厚く、就職支援のイベント、大学教員準備講座、大学教員インターンシップなどに参加することができます。以上のように本学や本研究科、あるいは本コースには、研究者として、そして 1 人の人間として成長できる環境があると感じています。

ラズグイ・ヨーズリさん(2022 年度博士後期課程修了)
イタリア Ca’Foscari University of Venice, Department of Humanities 卒業
研究テーマ:Football fandom
私が本研究科に進学することになったきっかけは、 5 年前の今の指導教員との出会いでした。当時はイタリアで博士前期課程を取ろうと考えていて、日本におけるサッカーサポーターについての研究を行っていました。前期課程の 2 年目で神戸大学に留学し、サッカーファンダムの研究に造詣が深い小笠原先生に出会い、それが今の研究を始めたきっかけとなりました。幅広い知識をお持ちの先生方はもちろん、 興味深い研究をされている研究者が数多く在籍する環境に恵まれ、アイディアやインスピレーションがいっぱい生まれる研究室に所属していることが貴重な経験の源になっていると感じています。
私自身の研究テーマとしては、ヴィッセル神戸のサポーター文化について調査しています。スタジアムでの観戦やサポーターの活動などを人類学研究でよく用いられる参与観察というメソドロジーを使いながら、 現代社会におけるサッカーの現代儀礼の分析を国際化との関連性から考察しています。 博士後期課程では、 必要な単位は少ないものの、 ゼミへの参加や先端社会論コースの授業を自由に受けることができ、 現代の問題について議論したり、アイディアを交換することで、ダイナミックな形で自分の研究に役立つインプットがたくさんいただけることも、とてもありがたいと思っています。
HUGHES Phillip さん(博士後期課程修了)
研究テーマ:Queer migration and drag performance in Japan: Rethinking identification, participation and belonging
現在、 兵庫県立大学国際交流機構(客員教員)
神戸大学国際文化学研究科に入学したきっかけは、 現代における社会問題とその背景にある事情を学ぶだけではなく、現在の日本と私の出身地であるイギリスやその他の国との関係を歴史的に遡りながら、 広い学際的視野で研究ができると考えたからです。
本研究科では、当事者研究を理論的にも方法論的にも肯定しつつ、日本における外国人研究者である自身をパラダイムとして、マジョリティ/マイノリティ、加害者/被害者、差別者/被差別者という位置づけを実証的に研究しました。そのような理論的視点から、LGBTQ 移住者の規範意識、セクシュアリティやジェンダーへの期待は、 移住を通じてどのように再形成されるのかを論じ、移住は日本の LGBTQ コミュニティ、文化、政治を変容させたことが明らかになりました。このような先進的課題を研究する私には、本研究科の先端社会論コースはぴったり合いました。
指導教員の青山教授のおかげで、教育現場でも、多様な価値観と広い視野を持ちながら、理論と実践の両輪を回しながら前に進めています。本コースで学んだ私が教員として教鞭を執り、今日の学生に伝えたいことは、「今日的課題の発見に努めると同時に、それらをアカデミックな研究の場に反映させる視野の広さと柔軟性を持ち合わせながら、学際的かつ多角的に研究することを通して、諸問題を共有することの重要性」であり、その重要性を教え伝えていくことを自身の使命とし、さまざまな能力を磨くようにこころがけています。

コース名の「先端社会論」っていう言葉はあまり聞いたことがなく、なじみがないのですが?
そうですね。「先端社会」ってどんな社会なの? と思われちゃうかもしれませんね。でも、「先端社会論」コースは、「先端社会を論じる」コースではなく、「先端的な社会問題を論じる」コース、っていう意味なんです。もう少し詳しくいうと、「現代社会の先端的な問題群に学際的に取りくむ」コースです。
ああ。そうだったんですか。だけど、「先端的な問題群」って、たとえばどんな問題ですか?
科学技術の進歩とか情報化、それにグローバル化とか、現代社会に特有な性格によって引き起こされている新しい問題群、っていったらいいかしらね。たとえば代理母問題とか、地球の温暖化みたいな環境問題とか。身近なところでは、男女の性差の意味あいがゆれ動いていることとか。
そういう問題だったら、ずっと気になっていたことにカブってくるかなあ。でも、さきほど「学際的に取りくむ」っていうお話でしたけれど、専門分野としてはどうなるんでしょうか?
専門分野っていう言い方をすると、今現在のコーススタッフは、社会学、カルチュラル・スタディーズ、ジェンダー論、法学、哲学、倫理学っていうことになるかしら。けれども、「学際的に取りくむ」っていうことは、そうした従来の分野が単独では扱いきれない問題に取りくむ、っていうことですから、あまり専門分野は気にしなくてもいいんじゃないかしらね。
それにしても、学部時代の専門とはだいぶんズレているんですが、だいじょうぶでしょうか?
この研究科には、そういう人のためにキャリアアップ型プログラムがありますし、入試問題に合格点が取れるだけの基礎学力があれば、あとは入学後の熱意と努力だと思いますよ。
すみません。私も質問していいですか。私はドクターまで進学したいという希望を持っているのですが、先端社会論コースの研究者養成型プログラムの入試はかなり難関なのでしょうか?
ドクター進学を考えているのなら、前期課程の入試よりもむしろ後期課程の入試に注意してください。募集人数を見てもわかりますように、前期課程に入学しても後期課程に進学できるとは限りませんから。研究者養成型プログラムを選択するのでしたら、前期課程・後期課程の5 年間で博士論文を完成させるつもりで、そのために必要な基礎学力をしっかり身につけておいてくださいね。