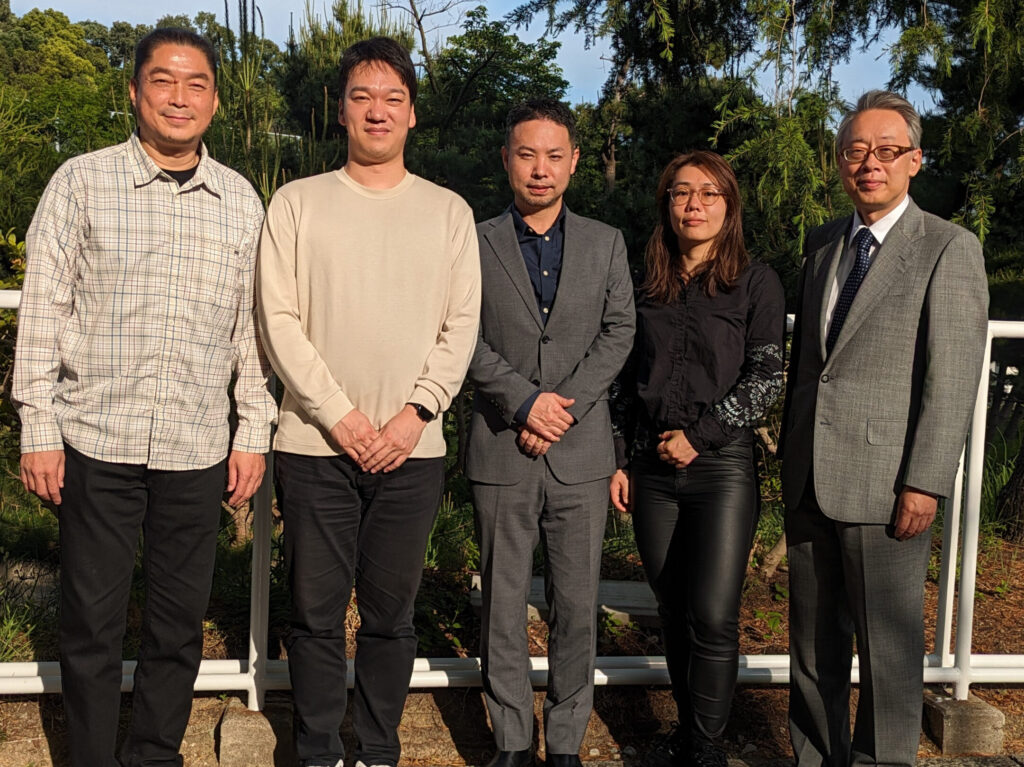最終更新日: 2025年10月15日
文化相関・地域文化系 ヨーロッパ・アメリカ文化論コース
ヨーロッパ・アメリカ文化論コースでは、近代以降、世界の政治・経済・文化などで中心的な役割を果たしてきたヨーロッパとアメリカの社会と文化について、多様な角度から総合的に教育・研究します。これらの地域で発展した文化は世界へと広まりましたが、現在、批判的に再検討されていることは周知の通りです。それに加えて、最近では、欧米の中にありながら近代成立の過程で周縁にあった社会と文化に関する研究も進展してきています。このコースでは、以上のような成果を踏まえて、現代の我々の生活と意識に深く根付いているように見える欧米的な思考や価値観を再検討し、その21 世紀における意義を探っていきます。歴史・言語・宗教・思想・文学・芸術・社会制度など、幅広い分野にわたって具体的な考察を積み重ねることで、いまだ知られざるヨーロッパやアメリカの深奥に迫りたいと思います。
| 進路実績 | (前期課程) 琉球新報、大和証券、日立製作所、三田市役所、関西電力、時事通信社、在外公館専門調査員、東洋電機製造、大成建設、ニトリ、浜松市役所、クボタ、神戸大学大学院博士後期課程進学、明星産商ほか
(後期課程) 静岡大学人文学部講師、佛教大学専任講師、神戸大学非常勤講師、神戸松蔭女子学院大学非常勤講師、大和大学非常勤講師、同志社大学非常勤講師、大阪市立大学非常勤講師、神戸大学国際文化学研究推進センター協力研究員ほか |
|---|
| 在籍学生数 | (前期課程) 8名
(前期課程) 4名 |
|---|
| 論文テーマ例 | グリム兄弟「ドイツ伝説集」
ウィリアム・モリス研究
「ハリー・ポッター」に見るヴィクトリア文化の受容
アメリカイタリア移民
ブロンテの自然観
I Love Lucyにおける視覚的ギャグの分析
ポルトガルにおけるミランダ語の成立
戦間期アメリカ合衆国における平和主義
孤立主義
ポピュリズム
英国庭園研究
イーヴリン・ウォーの 「ブライズ、ヘッド再訪」
アメリカの移民政策と中国系移民の現状 |
|---|
| 所属教員の紹介 | 小澤 卓也 教授 ラテン・アメリカ文化交流論特殊講義ほか
ラテンアメリカ、とりわけ中央アメリカの近現代史が専門です。最近はグローバルな歴史的視点に立ちながら、中米社会を大きく規定している民族問題や輸出作物生産文化の研究を進めています。 衣笠 太朗 講師 ヨーロッパ社会文化論特殊講義ほか
専門はドイツ=中東欧境界地域の近現代史であり、主に現在のドイツ、ポーランド、チェコの境界に位置するシレジア(シュレージエン/シロンスク/スレスコ)における分離主義運動や住民移動について研究しています。 中村 麻美 講師 イギリス社会文化論特殊講義ほか
英語圏、特に英国におけるユートピア・ディストピア文学ないしサイエンス・フィクション(SF)を専門としています。研究関心はノスタルジア、ジェンダー・セクシュアリティ、ポストヒューマン哲学です。 深町 悟 准教授 越境文学論特殊講義ほか
19世紀後半から第一次大戦ごろの英国近未来戦争小説(侵攻小説と私は呼んでいます)が英国内、あるいは海外でどのような影響を与えたかを研究しています。 |
|---|
今井 亜美さん(博士前期課程2年)
同志社大学文学部文化史学科卒業
研究テーマ:「20世紀メキシコ合衆国における「国民文化」創造の試み -アギーレ・ベルトランのアクルトゥラシオン理論の視点から-」
学部生時代は、他大学で歴史学を専攻していました。スペインによる新大陸への布教の歴史を研究する中で、ラテンアメリカ地域独特の歴史的背景と文化に魅了され、ラテンアメリカの歴史研究を志し、この研究科に進学しました。現在は20世紀のメキシコ合衆国における文化変容について研究しています。
メキシコと日本は地球を挟んでほとんど正反対に位置する国同士です。ですので、「そんな遠い国のことを研究する意味はあるの?」と聞かれることもあります。しかし、遠く離れた国の学生である私が研究するからこそ、発見できることや学べることがそこにはあると思い、日々研究に取り組んでいます。
国際文化研究科では歴史学だけではなく、政治学や文化人類学、社会学、文学、映画研究、観光研究など様々な分野で研究されている先生方や先輩方、同級生に囲まれています。国籍も様々で、講義や研究室での会話を通して毎日刺激をもらっています。一見、自身の研究にはあまり関係のないように思えるような研究や議題でも、話をしているうちにそこからヒントをもらえるということが多々あります。私のように「文化」という広大な概念を研究対象にしている人にとって、学際的な研究を行うことができる国際文化研究科は、とても貴重な環境だと思います。

王 芸萱さん(2023 年度博士前期課程修了)
瀋陽大学日本語学部卒業
研究テーマ:「メキシコの対中国貿易赤字問題の分析検討―中墨貿易のさらなる発展に向けて―」
学部時代ではラテンアメリカ文化について触れたことをきっかけに、ラテンアメリカに魅力を感じるようになりました。とりわけラテンアメリカ地域において、ブラジルに次ぐ経済大国であり、アメリカの重要なパートナーでもあるメキシコに対しては、これまでのほとんどない認識の上に、新たな認識が生まれました。また、学部 3 年次に交換留学を経験したおかげで、さまざまな異文化の人と知り合って、多文化共生の魅力を身をもって感じることができました。そのため学部卒業後は、専門的な知識をより深く知りたいと考えて、国際文化学研究科のヨーロッパ・アメリカ文化論コースに入学しました。
このコースには、ヨロアメの政治、経済、文化など幅広い分野の講義や演習をカバーしています。授業では学生の積極的で自由な発言に重視します。さまざまな専門性をもつ先生たちは、学生の考え方を重んじながら専門的な指導を行い、学生の研究を暖かく支えています。また、多国籍の仲間とのコミュニケーションやディスカッションの場にも恵まれていて、学術的な交流だけでなく、視野を広げることもできます。
在学中は、コースが提供してくれる優れた研究環境を深く実感し、充実や成長を味わう日々を過ごしました。
石井 昌子さん(2023 年度博士後期課程修了)
京都大学大学院文学研究科博士後期課程指導認定退学
研究テーマ:「ジョージ・エリオットのリアリズムと道徳観―シンパシーに乏しい人間の描写からの考察―」
現在、同志社大学嘱託講師・京都教育大学非常勤講師
私の博論は、19 世紀イギリスの代表的リアリズム小説家ジョージ・エリオット(1819–80)のリアリズムがこれまでの解釈と異なり、初期作品から後期作品に向けて進展していること、その背後には作者自身の道徳観の成熟があることを明らかにしました。
ヨロ・アメコースに入学する前の私は、研究は始めていましたが博論の書き方が分からず、京都大学の非常勤講師として英語を教えていました。しかし非常勤講師も定年に近い頃、同じく文学を研究している友人から神戸大学大学院の国際文化学研究科では、コロキアムやコース指導があって段階を踏んで書き進めて行けるという朗報を得ました。そしてこれが私にとって文学研究者として生きていく最後のチャンスだと思いました。
忙しいヨロ・アメの先生方が、専門の違う論文に目を通してコメントを下さったことには本当に頭が下がります。コース指導は厳しいものでしたが、そのおかげで徐々に私の博論が意義のあるものへと発展してゆきました。とくに指導教員の先生には感謝しています。
博論作成に当たってもう1 つ私の背中を押してくれたのは、海外のジャーナルです。私の博論の要となる議論は日本のジョージ・エリオット協会ではなかなか賛同が得られず、大いに困りました。しかしイギリスのジョージ・エリオット協会の機関誌に投稿したところ、当時の編集長で今の会長から、すぐにアクセプトのメールが届きました。「とても思慮深く面白い。ほかのメンバーも同感だろう」というコメントを得て私の博論は息を吹き返しました。
ヨロ・アメコースに集う学生の興味の対象は様々で、発表の場で彼らの多様な主張が徐々に洗練されてゆくのを見るのは面白く感動的です。博士課程前期 2 年もしくは後期 3 年の修業はきついけれど、努力すれば必ず成長が実感できます。
西田 悠さん(2022 年度博士課程前期課程修了)
法政大学社会学部卒業
研究テーマ:「現代キューバの人種主義からみる貧困の再生産過程 ―人種差別の社会問題化への取組みとその困難性」
現在、琉球新報社勤務
学部への入学以前に関心を抱いていたラテンアメリカの歴史・思想・現代社会の在りようについて、専門性を伴って探究したいと考え、本研究科への進学を決めました。学部では社会学的なモノの見方に魅了され、特に日本国内外で展開されるグローバル化が、多種多様な社会集団に対してどのような作用をもたらしてきているのかといった点ついて、幅広く関心を寄せていました。
本研究科では、国民国家や人種、ジェンダーなどに係る社会学的視座を基軸としつつ、歴史学・人類学・哲学あるいは社会思想といった研究領域を学際的に学びました。このような学問生活は、自らの社会的な立場性と研究対象であるキューバにおける人種ー貧困問題を繰り返し往復して、オリジナルな研究を展開しようという目論みにおいて、非常に有効なものでした。
多種多様な専門的知識・技能の養成にご尽力いただいた教員方はもちろんのこと、本研究科であったからこそ巡り会えた仲間たちの存在についても、修了後の私の生き方を方向づける大きな要素となっていくと思います。
地球の反対側に位置するキューバ社会について探究しながらも、いまここで私が成すべきことは何かを考え続けたことが進路選択にも活き、最終的に本課程で経験したことの多くに意味を持たせることができました。
専門領域へのこだわりと学際的な広い関心をお持ちの方に是非お勧めしたい研究科です。

社会人ですが、仕事をしながらの入学は可能でしょうか?
規定年限で修了を目指す場合、博士前期課程では少なくとも1 年次においては週に1~2回以上の登校が必要ですが、「長期履修制度」を利用すれば最長4年まで修了年限を伸ばせますので、登校日と学期毎の履修単位をかなり少なくすることができます。また、博士後期課程の場合は、指導教員との相談により柔軟な受講が可能な場合もあります。
外国語の知識はどの程度必要ですか?
英語の文献が読める程度の知識は必要です。どこかの地域に関することを専門的に研究する場合は、当該地域の言語の知識を持っている必要があります。前期(修士)課程の「キャリアアップ型プログラム」では、それほど高度な外国語力がなくても大丈夫でしょう。
専門の先生がいない地域や領域のことを研究テーマにすることはできますか?
ある程度柔軟に対応することができます。受験を考えている場合は、いずれかの教員と連絡を取って、具体的なテーマについて相談してください。